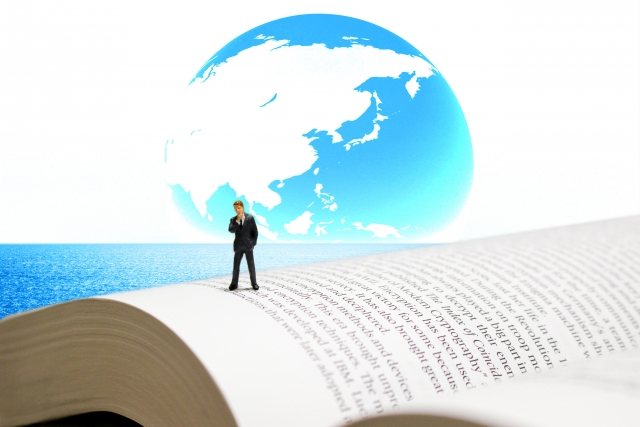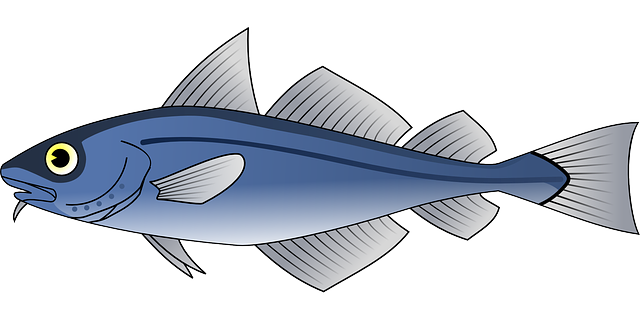
魚アレルギーの対応は簡単ではない。
■ 魚アレルギーは、自然に改善することが少なく、種類も多いために経口免疫寛容誘導療法(少しずつ摂取して食べられる量を増量する治療法)はなかなか難しい面があります。
■ 実際には、私も魚に関しての免疫寛容誘導療法をする経験がそれなりにあり、今回の症例報告と同じように、スキンプリックテストや特異的IgE抗体価をみながら、行っています。
| P: 生後9ヶ月時に初めてメルルーサを摂取して全身蕁麻疹を来たし、その後誤食により4回の即時型アレルギー反応(アナフィラキシーを含む)をきたしていた6歳女児
E: 凍結乾燥メルルーサによる経口免疫療法 C: - O: メルルーサによる免疫療法は他の魚の免疫寛容も誘導するか |
D'Amelio C, et al. Induction of tolerance to different types of fish through desensitization with hake. Pediatr Allergy Immunol 2016. [Epub ahead of print]
結果
■ 皮膚プリックテスト(SPT)は、メルルーサ[14×10mm]、アナゴ、サケ、マグロ、アンコウ、ハタ、Megrim、サーディン、カサゴで行われた。 総IgE 28.7kU/l、特異的IgE抗体価 メルルーサ 3.31kU/l、コイ・パルブアルブミン4.87kU/lだった。
■ メルルーサに対する経口食物負荷試験(OFC)は256mg摂取後、腹痛をきたし、陽性だった。
■ メルルーサは、冷凍肉(メルルーサ80gが16.2gのタンパク質を含有)を使用し、凍結乾燥しされたものを使用した。
■ 増量フェーズは11ヶ月間で、経過中、アドレナリンを必要とするアナフィラキシーを1回(おそらく中耳炎に関連)、中等度の腹痛を4回来たした。
■ 維持フェーズで患者は2-3日ごとに40gのメルルーサを摂取し、13ヶ月時に80g、18ヶ月時に160gの負荷で耐性を確認された。
■ 他の種類の魚(バス50g、マグロ50g、アンコウ50g、シタビラメ40g、アナゴ50g)にも耐性が確認された。
■ 維持フェーズの5ヶ月後と12ヶ月後に、軽度の腹痛を呈したが、量を減量して改善した。
■ 現在は、患者は週3回、80gのメルルーサを摂取し、週に2回、マグロ、アンコウ、バス、シタビラメ、アナゴを交代に代わりに摂取しているが、症状はない。
■ 皮膚プリックテストは経時的に改善した。
コメント
■ 魚は小児の食物アレルギーの原因のうちの1つですが、牛乳や卵アレルギーに比較して持続する傾向があります。
■ 卵や乳、ピーナッツの経口免疫寛容誘導に関してはそれなりに論文が増えてきていますが、魚に対する経口免疫寛容は、現実的には種類が多いため難しいと考えられており、報告も少ないです。
■ 今回の報告は、メルルーサの耐性が誘導されると、他の魚の耐性も誘導されていたとまとめられ、メルルーサ以外の魚に対する耐性誘導は、主要アレルゲンであるパルブアルブミンの広い交差反応性に起因するためかもしれないとされていました。
■ ただ、中断してどうかという検討はこの論文は検討していませんし、維持フェーズで食べ続けることを指導しています。
■ あくまで経験上は、長期間続けていても、中断が長くなると再燃することが多いようです。
■ この論文を読んで、自分自身で診ている患者さんの症例報告をしておいたほうが良いだろうかと思いました。