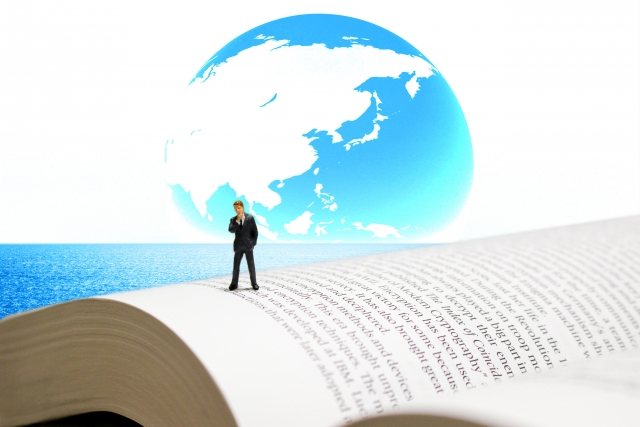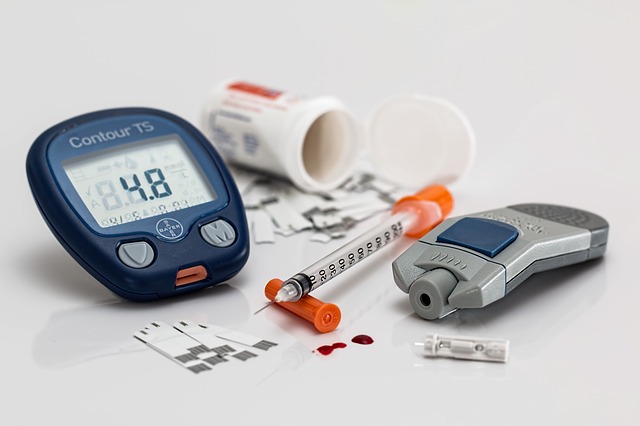
■ 多くの疾患で、検査が病気の診断の補助として使われるわけですが、アトピー性皮膚炎は基本的に臨床診断(それまでの経過や症状で診断する)ことになります。
■ そして、アトピー性皮膚炎の検査として有力なものとして、TARCに関していくつかの報告をご紹介しています。
外観上アトピー性皮膚炎がなくても、バリア機能に異常があればTARCが上昇する
血清TARCは、重症薬疹(DIHS)の診断に役立つかもしれない
■ TARC以外にも多くのバイオマーカーが研究されており、そのシステマティックレビューをご紹介いたします。
E: -
C: -
O: 各種バイオマーカーは、アトピー性皮膚炎の診断や重症度の判定に役立つか
結局、何を知りたい?
✅アトピー性皮膚炎の診断や重症度を測ることのできる検査法をしりたい。
■ 計222の研究で115種類の様々なバイオマーカーが報告されていたが、結果として、108論文における64のバイオマーカーが、メタアナリシスのためのデータを報告していた。
■ 30種類のバイオマーカーを検討した縦断研究から、少なくとも4つの研究を含む、血清thymus and activation-regulated chemokin(TARC/CCL17)、血清総lgE、血清eosinophil cationic protein(ECP)、血清sE-セレクチンでメタアナリシスが実施された。
■ 49種類のバイオマーカーを調査した横断研究82件がメタアナリシスで検討されており、少なくとも4つの研究がある、TARC、ECP、総lgE、CTACK/CCL27、CD30、IL-18、LDH、MDC、ビタミンDに対しメタアナリシスが実施された。
■ 総IgEは、縦断的研究からのプールデータから、相関係数0.33(95%Cl 0.08-0.64)と弱い相関であり、横断研究のメタアナリシスでも、0.45(95%CI 0.32-0.57)と中等度の相関だった。
■ 血清TARCは、4件の縦断研究と16件の横断研究からアトピー性皮膚炎重症度と有意に相関すると判明し、相関係数は、縦断研究(r=0.60、95%CI 0.48-0.70)および横断研究(r = 0.64、95%のCl 0.57-0.70)と、強い相関を示した。
■ CTACK/CCL27は、T細胞を引き付ける皮膚炎症に重要な役割を果たすと示唆される、もうひとつのケモカインであるが、血清CTACKは16例の患者の縦断研究による2つの研究で報告されるのみだった。メタアナリシスは重症度(r=0.68、95% CI 0.47-0.82)に、強い相関を示した。
■ 血清sE-セレクチンは血管内皮の上で産生される細胞接着分子であり、4つの縦断的研究が相関係数を報告しており、0.44(95%CI 0.23-0.62)で中等度の相関を示した。
■ ECPは、好酸球の脱顆粒中に放出されるタンパク質であり、血清ECPは縦断的研究でしばしば測定されたが、相関係数0.34(95%CI 0.08-0.56)で、横断研究では相関係数0.43(95%のCl 0.28-0.56)だった。
■ MDC/CCL22は、CCR4を発現している化学遊走物質であり、横断研究において血清MDCは、相関係数0.66(95%CI 0.52-0.77)であり、縦断研究は研究数の不足(2研究)により実施できなかった。
■ LDHはほとんど全ての組織細胞で見つかる酵素で、ピルビン酸から乳酸への触媒作用を及ぼし、4件の横断研究では血清LDHの相関係数を報告し、相関係数0.51(95%Cl 0.38-0.62)だった。
■ IL-18に関する横断研究のメタアナリシスは、相関係数0.68(95%CI 0.15-0.91)と、高い相関係数を示した。しかし、横断研究4件のみの報告であるうえfunnel plotは左右非対称であり、信頼できない可能性があった。縦断的研究1件のみが血清IL-18と重症度の間に有意の相関を報告した。
■ 血清可溶性CD30は、アトピー性皮膚炎重症度と逆相関(-0.74)から非常に強い相関(0.96)まで、広く変動し、相関係数0.39(95%CI-0.21~0.77)になった。
■ ビタミンDは、も相関係数(0.12~ -0.88)が広範囲にわたり、メタアナリシスは、相関係数-0.32(95%CI-0.64~0.09)だった。funnel plotは左右非対称であり、CD30もビタミンDもアトピー性皮膚炎の重症度のためのバイオマーカーとして不適切であると判断された。
■ IL-2R、IL-4R、IL-31はAD重症度と良好な相関を示すが、研究が少なく、その他のバイオマーカーは、さらに少ない研究結果なうえ、不確実な結果だった。
結局、何がわかった?
✅十分なメタアナリシスができた検討から、アトピー性皮膚炎の重症度と相関があったバイオマーカーは血清TARCであり、縦断研究で相関係数 0.60、横断研究で相関係数 0.64だった(1に近いほど、検査と重症度の相関がある)。
■ 現在のところ、血清TARCが利用可能な最も信頼性が高いバイオマーカーであると結論されていました。
■ 血清TARCは、縦断的研究で相関係数0.60(95CI 0.48-0.70)、横断研究の相関係数0.64(95%CI 0.57-0.70)であり、様々な研究の多数の患者数で決定されたとまとめられています。
■ 有用ではあるものの、さらなる研究を要するのがCTACK、E-セレクチン、MDC、LDH、IL-18だったそうです。
■ 相関係数0.6~0.64ですから、悪くはないけど、すごくいいというわけではないという程度ですね。実際、明らかに湿疹がひどいと思ってもTARCが低めだったり、皮膚がきれいと思ってもTARCが高め、ということがあります。
■ その原因がどこにあるのかは私にも十分理解できているわけではありませんが、TARCは皮膚ばかりでなく消化管から産生されたり(アレルギー 2012; 61:970-5.)、乾燥程度でも上昇したり(上記)、皮膚に湿疹がない出生時にすでに上昇している(Clin Exp Allergy 2011; 41:186-91.)ことも指摘されています。
■ 現在はTARCが保険適応もあることから、とても有用な検査ではありますが、TARCのみで多種多様な原因を持つアトピー性皮膚炎のバイオマーカーをすべて担うのは難しい面もあるでしょう。
■ 明日は、それらのバイオマーカーを単一ではなく複数を組み合わせたらどうかという報告をご紹介いたします。
今日のまとめ
✅血清TARCが利用可能な最も信頼性が高いバイオマーカーであるが、他のバイオマーカーも有望なものがあり、今後の検討を要する。