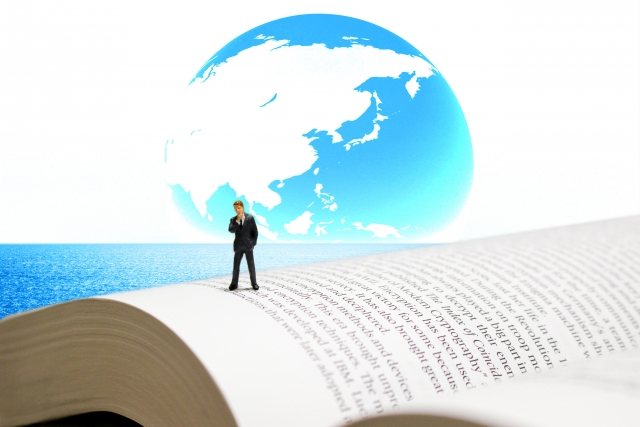Nair P, et al. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. N Engl J Med 2017; 376:2448-58.
生物学的製剤の臨床研究結果が次々と発表されています。
■ 生物学的製剤に関する報告は急増しています。
■ 最近、メポリズマブ(ヌーカラ)に関してのご紹介をしたばかりです。
ヌーカラは、好酸球性重症喘息による入院率を約半分にする: メタアナリシス
■ そんな中、今度は ベンラリズマブ(ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤)に関する報告がNEJMに発表されました。
■ すでに先行したLancetの検討と同様、好酸球性増多のある喘息に対し有効であるという結果です。
E1: ベンラリズマブ 30mg/回 皮下注 4週間ごと
E2: ベンラリズマブ 30mg/回 皮下注 8週間ごと (最初の 3 回は 4 週ごと)
C: プラセボ
O: 28週間の経口ステロイド薬使用量を減量するか
![]() 結局、何を知りたい?
結局、何を知りたい?
✅ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体であるベンラリズマブが好酸球性喘息発作を減少させるかということを知ろうとしている。
ベンラリズマブは経口ステロイド減量に効果があるか?
■ 投与前と比較して、プラセボ群において経口ステロイド使用量の中央値が25%減少したのと比較し、ベンラリズマブを投与した2群は、75%有意に経口ステロイド投与量が低下した(両群比較;P < 0.001)。
■ 経口ステロイド使用量の減少のオッズは、プラセボ群よりベンラリズマブ群で4倍以上高かった。
■ セカンダリアウトカムにおいて、8週間ごとのベンラリズマブ投与群は、プラセボ群より喘息増悪率が55%少なく(marginal rate, 0.83 vs. 1.83, P = 0.003)、4週間ごとのベンラリズマブ投与群はプラセボ群より70%少なかった(marginal rate, 0.54 vs. 1.83, P<0.001)。
論文から引用。Aはステロイド内服、Bは喘息発作。
■ 28週時点において、いずれのベンラリズマブ投与群も、プラセボと比較しFEV1の有意の改善は認められなかった。
■ ベンラリズマブ群で有意な変化を示している指標も、有意な変化を示していない指標もあり、喘息に対するさまざまな計測指標は色々だった。
■ 不都合なイベント頻度は、各ベンラリズマブ群とプラセボ群において同程度だった。
 結局、何がわかった?
結局、何がわかった?
✅6か月間のベンラリズマブ皮下注は、好酸球性喘息のステロイド内服量を75%減量し、喘息発作も減らした。
ベンラリズマブは、呼吸機能は改善させないものの好酸球性喘息発作を減らす。
■ ベンラリズマブは、プラセボと比較して経口ステロイド減量と増悪率に対し有意に臨床的なベネフットが示唆され、これらの効果は、FEV1に対する効果なく認められたとまとめられていました。
■ すなわち、呼吸機能には明らかな効果はなかったものの、ステロイド内服や喘息増悪を減らしたということですね。
■ これまでの生物学的製剤以外の報告は、どちらかというとLABA追加の報告が増えてきていましたが、これは呼吸機能そのものを改善させることにより発作を減らすという方法といえます。
小児喘息のコントロールは、フルタイド連日/屯用/シングレアのどれが良いか?(INFANT試験)
■ 生物学的製剤は、また異なるアプローチをしていて、さらにその効果はタイプを選ばなくてはならないのだと言えましょう。
![]() 今日のまとめ!
今日のまとめ!
✅ベンラリズマブは、呼吸機能は改善させないものの好酸球性喘息発作とステロイド内服量を減らす。